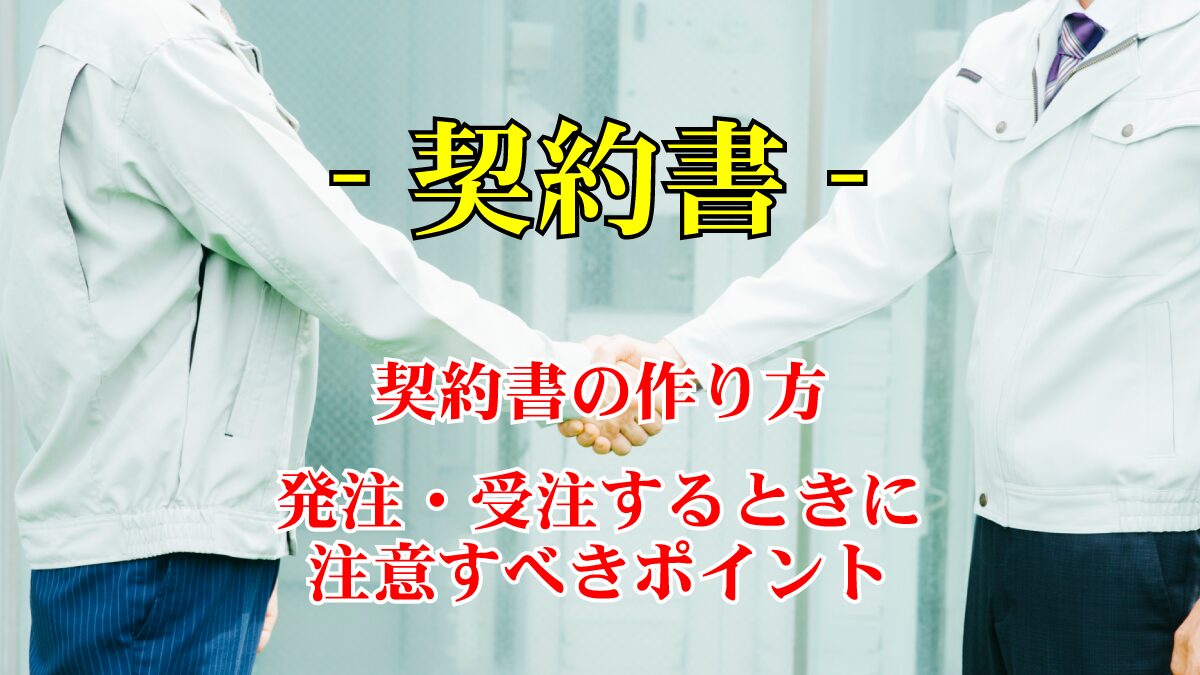はじめに
契約書はなぜ重要?
一人親方として元請けから仕事を請け負うとき、あるいは元請けが外注先として一人親方に業務を依頼するとき、契約書を作成しておくことは極めて大切です。口頭でのやり取りや慣習的なやり方に頼っていると、後から「言った・言わない」というトラブルが起きかねません。書面によって双方の役割や責任、報酬条件を明確化しておくことで、安心して仕事を進められる環境が整います。
- 一人親方と元請けの契約形態の概要
- 契約書に盛り込むべき必須条項と注意点
- 双方が押さえておきたいリスク管理や手続きフロー
本記事では、元請け・一人親方の両方に必要な視点を盛り込みながら、契約書を作成する際の具体的なポイントを解説していきます。
一人親方と元請けの契約形態の基本
雇用契約と請負契約の違い
建設業や各種工事業などでは、一人親方との間で多くの場合「請負契約」が結ばれます。
請負契約(業務委託契約)
一人親方は独立事業者として、工事や作業を完成させる義務を負い、元請けはその成果物に対して報酬を支払う形態。
労災保険に関しては通常の労災保険とは異なり、「特別加入」の仕組みがある。
雇用契約
一人親方ではなく、元請け企業の従業員として扱われる場合に該当。給与や社会保険などが適用される。
偽装請負リスク
一人親方と請負契約を結んでいるつもりでも、実際には元請けから「指示・命令」が強く、実態が“雇用”に近い場合があります。
元請け側のリスク
違法な偽装請負とみなされると、労働基準法や社会保険関連法違反等のペナルティを受ける可能性がある。
一人親方側のリスク
自分は一人親方として契約していたつもりでも、実は雇用と判断されると税務上や保険手続き上での混乱が生じる。
「どの範囲まで元請けが指示できるか」を契約書内で明確化し、請負の実態を保つように気をつけましょう。
契約書の基本構成と必須条項
契約書に盛り込むべき主な項目
- 契約当事者の情報
- 元請企業・一人親方双方の氏名(名称)・住所・連絡先を正確に記載
- 契約の目的・作業内容
- 請け負う工事や業務の範囲、具体的な作業内容を詳細に明記
- 契約期間・工期
- 着工日、完了予定日など期間を定める
- 報酬額・支払方法
- 結果払い、出来高払いなどの形式
- 支払いのタイミング(前金・中間金・完了後 など)
- 安全配慮義務・事故発生時の責任分担
- 労災保険の加入状況を含め、どこまで元請がサポートするか
- 解除条件・違反時の対応
- 契約を解除できる条件、損害賠償責任など
- 紛争解決方法
- 何か問題が起きたときにどの裁判所や仲裁機関を利用するか
- 再委託・下請の可否
- 一人親方がさらに別の人を雇う場合などの対応
事前に十分話し合った内容を、漏れなく文書化しておきましょう。あいまいな表現はトラブルの原因になりやすいです。
元請け側が注意すべきこと
安全管理・安全配慮義務の範囲
元請企業は、事故防止のために工事現場の安全管理を行う義務があります。
- 一人親方が労災保険に加入しているか確認する
- 安全書類(KY活動や安全計画書)の作成と共有
- 工事の手順や危険箇所の周知徹底
一人親方が作業中に事故が起きた場合でも、元請けの指示や安全管理の不備が認められれば、元請けが損害賠償を請求される可能性があります。
作業状況の確認と指示の境界線
仕事の進捗管理は必要ですが、過度に細かい「指示・命令」を出すと雇用契約とみなされる危険性があります。
- 作業開始前に成果物や工期を明確に合意しておく
- 日々の指示は「必要な安全上の注意」「成果物のチェック」にとどめる
支払条件・報酬計算の明確化
- 工事費用や材料費をどちらが負担するか、事前に協議して契約書に盛り込む
- 工期が長引いた場合の追加コストの扱いを明示しておく
一人親方が注意すべきこと
自分の保険加入状況を明示する
- 労災保険特別加入している場合は、加入証明書等を元請けに提示する
- 現場によっては、元請けが保険証明を求めることもあるため、常に更新しておく
業務範囲・追加業務が発生したときの対応
工事の途中で追加作業が発生した場合、契約書に書いていない分の報酬や期間が不明確になりがちです。
- 追加で発生した業務は、改めて「追加契約書」を交わすか、メールで合意内容を残すなどの対策が必要
事故・トラブル発生時の連絡フロー
- ケガ・事故が起きたら速やかに元請けに報告し、必要書類を整備する
- 保険申請時の手続きフローをあらかじめ把握しておくとスムーズに対応できる
契約書作成の実務ステップ
1. 契約前の打ち合わせ・見積もり
- 現場の内容や作業範囲を詳細に確認
- 見積書との整合性を取りつつ、どこまで責任を負うかを明確化
2. 書面作成・相互確認
- 契約書のテンプレートを利用する場合でも、専門家(行政書士・弁護士)にチェックしてもらうと安心
- クラウドサインなどの電子契約システムを使うと、更新時や保管時の手間を省ける
3. 押印・保管・更新
- 保管期間は最低でも5年~10年程度を目安に(必要に応じて法令を確認)
- 長期案件では、定期的に契約内容を見直し、変更があれば追加契約書を締結する
トラブル事例と対処法
よくあるトラブル例
- 追加工事の費用が合意されていない
- 口頭で追加依頼をされ、後から報酬面でもめる
- 安全管理を怠ったとして損害賠償を求められる
- 一人親方が事故に遭った際に、元請けが責任を問われる
- 支払い時期が不明確で未払いトラブル
- 契約書に支払期日の明記がなく、請求書提出後いつまでも支払われない
対処法・予防策
- 契約書に詳細を明示し、追加工事が発生したら追加書類やメールでの合意を残す
- 双方が安全管理・保険加入状況を可視化して、定期的に情報共有を行う
- 支払期日は必ず明記し、違反時のペナルティや遅延損害金に関する規定を設ける
チェックリスト・テンプレートの活用
元請・一人親方双方で確認すべきポイント(例)
- 作業内容・範囲は具体的に書かれているか
- 工期は明確か(着工日・完了日・納期など)
- 報酬の支払方法・支払時期・金額が記載されているか
- 安全管理責任や事故発生時の対応フローを確認しているか
- 一人親方の保険加入証明書は確認済みか
- 追加・変更工事の扱い方が決められているか
- 紛争解決方法(仲裁・管轄裁判所など)が書いてあるか
テンプレートとしては公的機関や業界団体のサイトが参考になります。最終的には、現状に応じてカスタマイズし、専門家のチェックを受けるのが望ましいです。
まとめ・おわりに
契約書をきちんと取り交わすことで、元請けと一人親方の双方が安心して仕事を進められます。口頭のやり取りや慣習頼りではなく、明文化したルールがあることで、責任や費用負担が明確になり、いざというときのトラブルも最小限に抑えることが可能です。
今後のアクション例
- 現在の契約書を定期的に見直し、リスクや実態の変化に合わせて更新する
- 事故やトラブルが起きた際は、早めに社労士や弁護士などの専門家に相談する
お互いの立場を尊重しながら、正確な契約書を作成し、円滑な取引関係を構築していきましょう。
補足・参考リンク
- 労災保険や特別加入に関する詳細: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html
- 契約書のテンプレート配布サイト:
https://jtuc-network-support.com/useful-links/usli-cont
https://biz.moneyforward.com/contract/templates/terms/

全国建設業親方労災保険組合では、労災保険にかかわるすべての申請書類作成を無料で代行しています。
加入や脱退においては「特別加入承認団体」を通じ申請します。
ですから、ほとんどの労災保険取扱団体では、申請書類の作成を代行しています。
特に、労災事故が発生したら、加入している団体や組合にすみやかに労災事故報告を行いましょう。
全国建設業親方労災保険組合は、加入から脱退、労災事故報告の連絡が入れば即座に対応しています。
専門家がスピーディに、しかも「無料」であなたをサポートします。
万が一に備えるなら、全国建設業親方労災保険組合で安心安全なサポートを受けましょう。